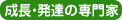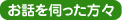子どもの慢性的な鼻づまりは大丈夫?

アレルギー性鼻炎などが引き金となり、慢性的な鼻詰まりに悩まされる子どもは少なくありません。
そんな中、子どもの慢性的な鼻詰まりが脳の発達や機能に悪影響を与える可能性があることが、東京大学の研究により明らかになりました。
そこで今回は、鼻詰まりの原因となる病気や鼻詰まりがもたらす影響についてご紹介します。
子どもの鼻づまりの原因
鼻詰まりの原因といえば、アレルギー性鼻炎が代表的ですが、他にも以下のような疾患が挙げられます。
- (1)副鼻腔炎
- 鼻の奥にある副鼻腔に細菌が感染することで炎症が起こる疾患。
膿性の鼻汁や鼻詰まり、頭痛や夜間の咳が特徴的な症状。 - (2)アデノイド肥大
- アデノイドという鼻の奥にあるリンパ組織の塊が大きくなる疾患。2~6歳頃の子どもによく見られ、鼻詰まりやいびき、中耳炎などの症状が現れる。
- (3)鼻中隔湾曲症
- 鼻の穴を分ける仕切り部分の鼻中隔が左右どちらかに曲がっている疾患。風邪や副鼻腔炎などの病気ではないのに、慢性的な鼻詰まりが続く場合は、鼻中隔側弯症が疑われる。
こういった疾患以外にも、寒暖差や化学物質などが原因で鼻詰まりを引き起こすこともあり、原因に合わせた治療が必要です。
慢性的な鼻詰まりが発達期の脳機能に影響
鼻が詰まって空気の通り道が狭くなると、結果的に肺に取り込まれる酸素量も減ってしまいます。
このように鼻呼吸が障害されることで、睡眠障害や記憶・学習能力の低下、歯並びや噛み合わせの乱れなどに悪影響を与えることは既に知られていました。
しかし、脳の機能にどのような影響を及ぼすかは明らかになっていません。
そこで、今回東京大学では脳の発達や機能に対する鼻呼吸障害の影響を調査するため、マウスによる実験を行いました。
その結果、慢性的な鼻呼吸障害の状態にしたマウスは、発達期において運動能力の低下やうつ病に似た症状や行動が増加していました。こうした症状は、成熟後のマウスでは見られなかった一方で、生後3日目〜3週目という早期発達期における鼻呼吸障害は抑うつ行動と関係し、3〜7週目の発達期における障害は運動能力の低下と関係していることが分かりました。
実際に、鼻呼吸障害と脳との関連を調べると、神経回路の形成阻害や神経細胞の異常な活動などが見られることから、慢性的な鼻呼吸障害は発達期において脳機能に影響を与えることが示唆されます。
子どもの鼻詰まりは、QOLの低下はもちろんのこと、集中力や睡眠の質の低下、さらには脳機能に影響を与えるリスクもあることを踏まえて、適切な治療を受けることが大切だと言えるでしょう。
参考URL
『時事メディカル』https://medical.jiji.com/topics/3718
 MR(医薬情報担当者):編集部スタッフ:古谷祥子
MR(医薬情報担当者):編集部スタッフ:古谷祥子