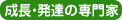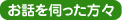まずは、医療を必要としているかどうかを判断するために、医師に相談しましょう
伸びない原因が分かり、更に医療が必要なほど伸びに問題がある場合には治療が必要となります。下記に、いくつか原因を載せましたので、参考にして下さい。
成長ホルモン分泌不全性低身長症
成長ホルモン分泌不全性低身長症(下垂体性小人症)は、脳下 垂体から分泌される成長ホルモンの分泌が障害されているために、身長の増加に異常をきたす病気であり、放置すると、身長が130cm程度で止まってしまうこともあります。成長ホルモン分泌不全性低身長症の小児は知能は正常で、また、体の均整がとれているため、背が低く幼いこと以外は他の小児 と異なりません。成長ホルモン治療を受けることによって、身長が伸びる可能性があります。
ターナー症候群
ターナー症候群は染色体の中のX染色体でのトラブルなので、女性だけに起こる病気です。低身長、二次性徴欠如(乳房が大きくならない、初潮が来ない)、外反肘(上腕に比べて前腕が 外側を向く)、翼状頸(頸部両側にひだ状の皮膚がある)などの症状を認めます。放置すると低身長は140cmに達しないことが多いです。 成長ホルモン治療を受けることによって、身長が伸びる可能性 があります。
思春期早発
思春期が、あまりに早すぎると、あっという間に大人になってしまい、身長が伸びなくなります。思春期を遅らせる治療をします。本来思春期(生殖機能の発育を含めて急速な身体的精神的な変化がおこる、人生のある時期のこと)におこる身体的特 徴が早期に発達すること。思春期は、正常では少年では13歳から15才、少女では9才から16才の間で始まります。思春期早発症では、この年齢に達する前に思春期が始まります。
他にも、栄養不足や過多、運動不足、睡眠不足、肥満、などなど、治療ではなく生活習慣に問題がある場合がありますので、その場合は、普段の生活の中で、できるだけ背が伸びるように可能性を高めて下さい。